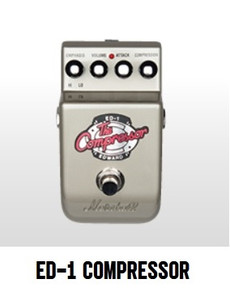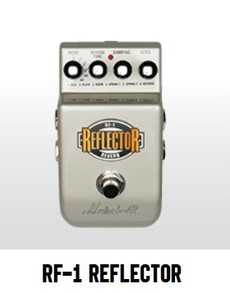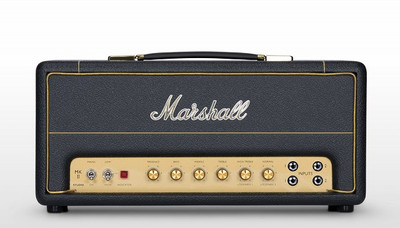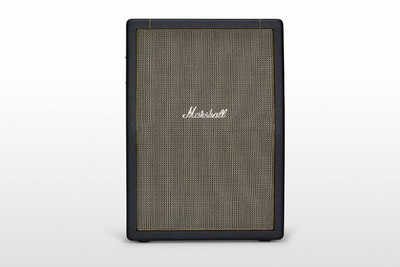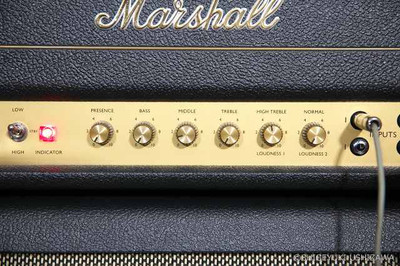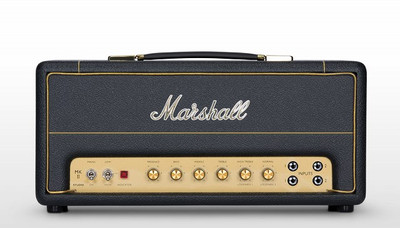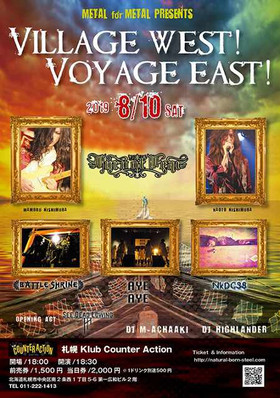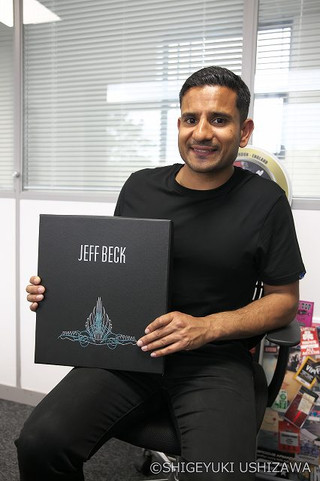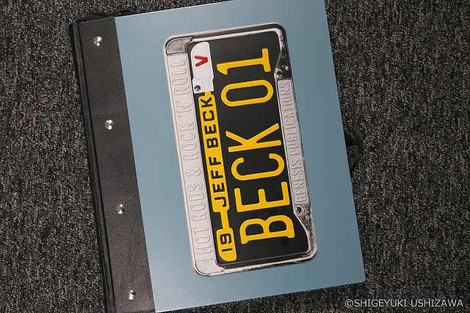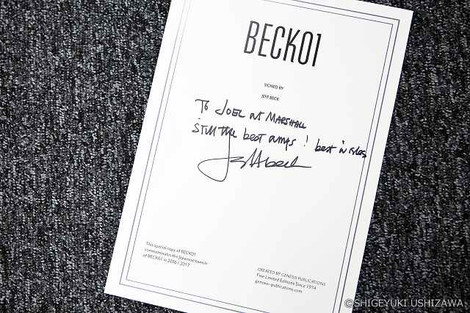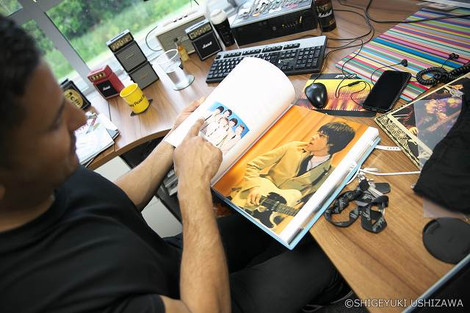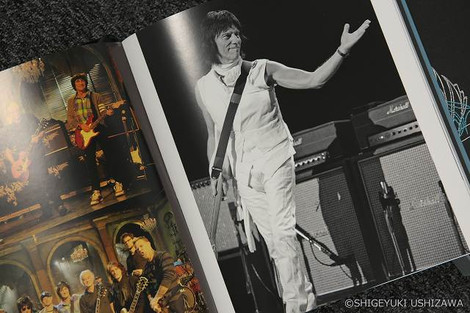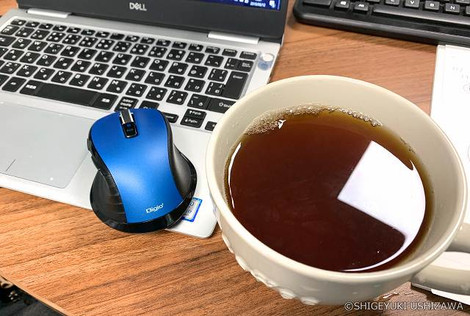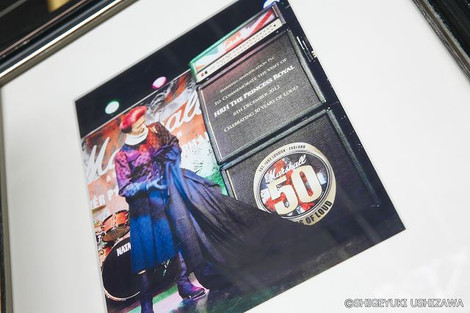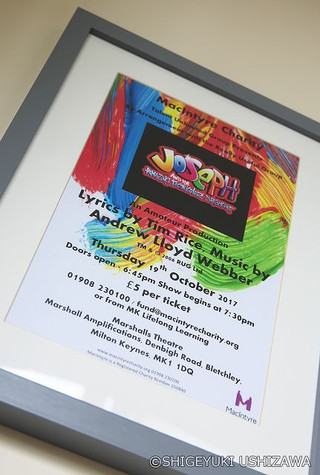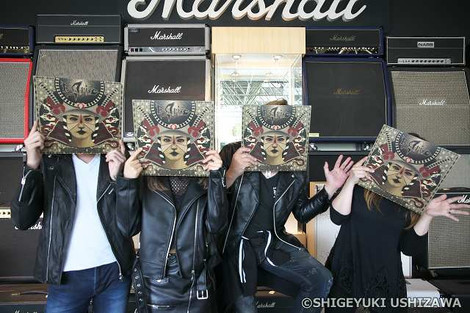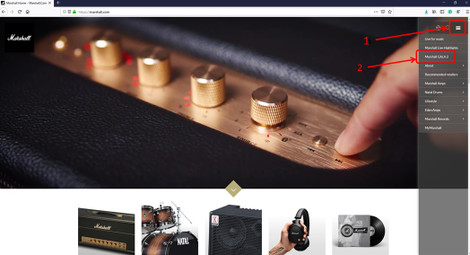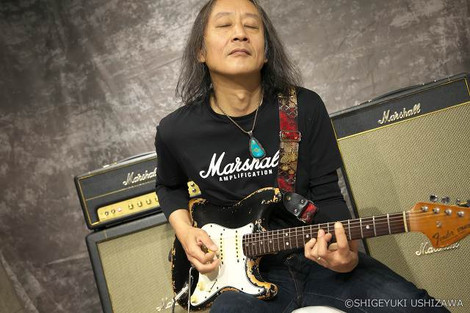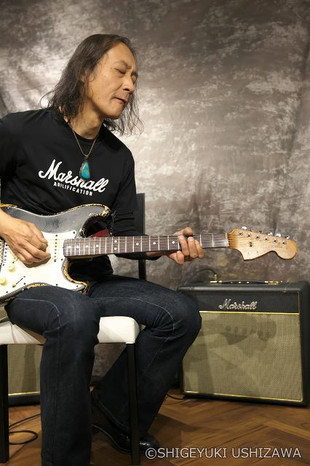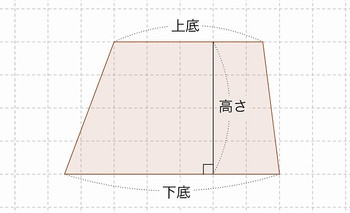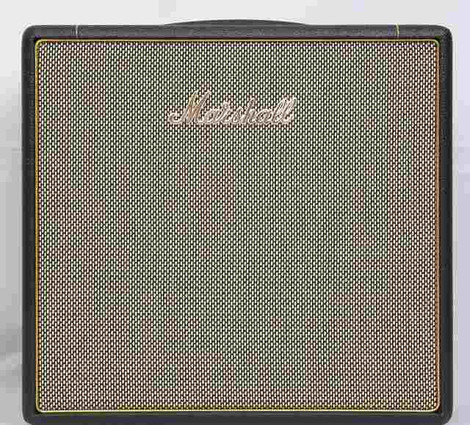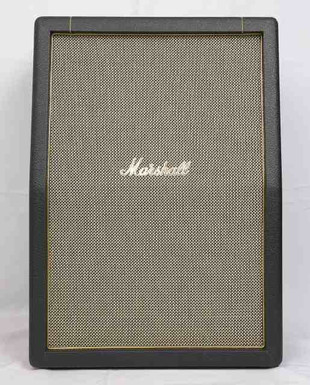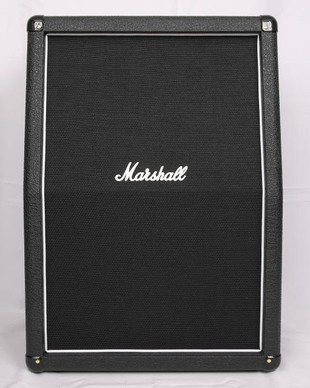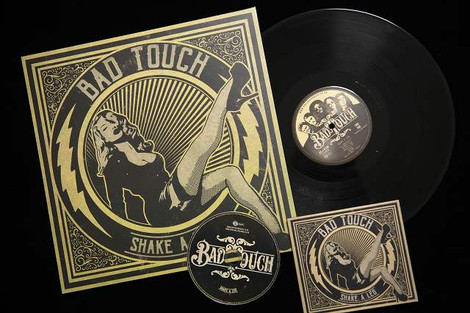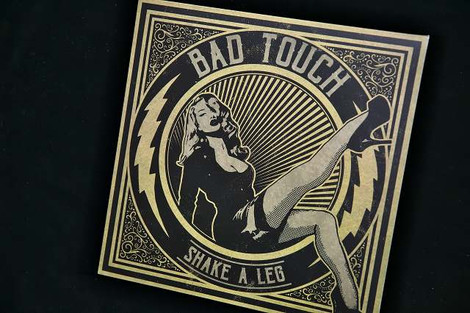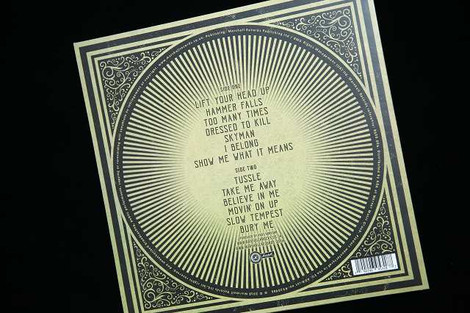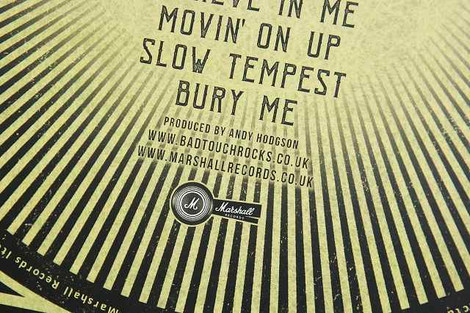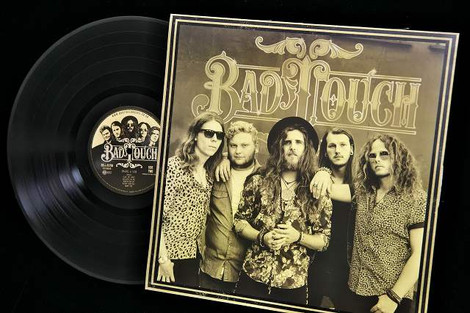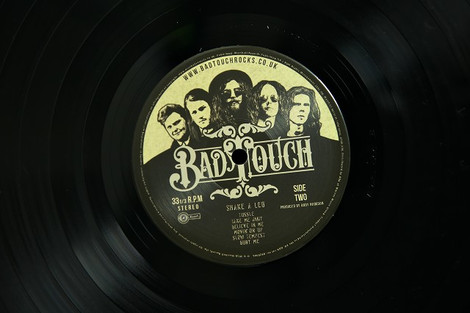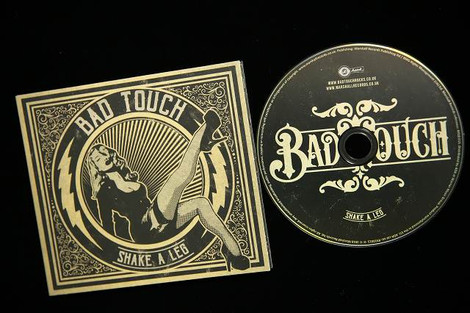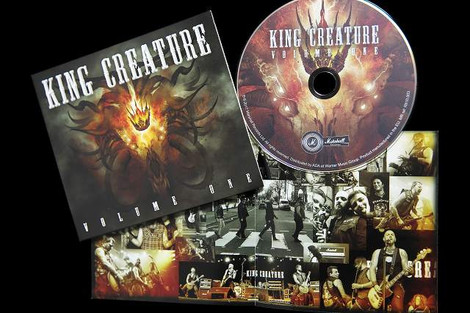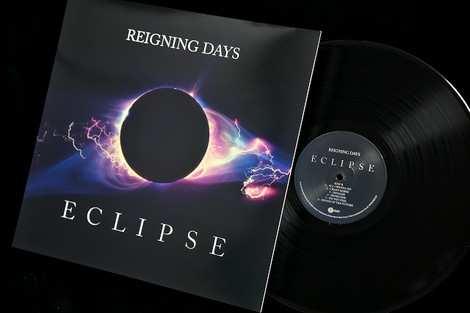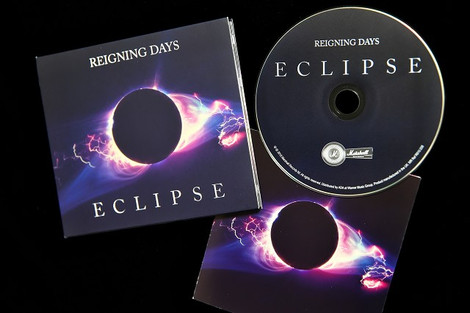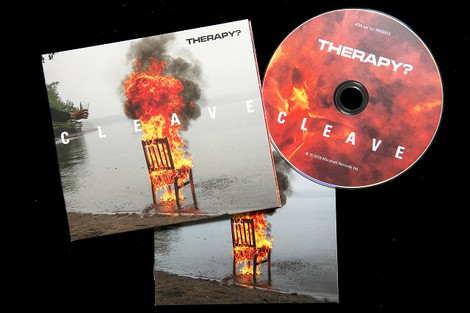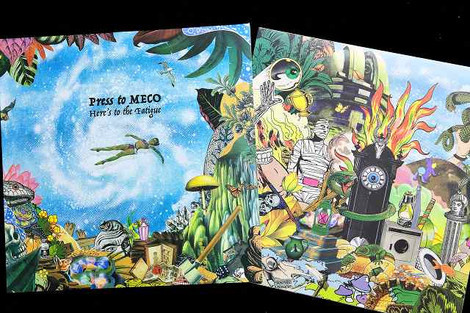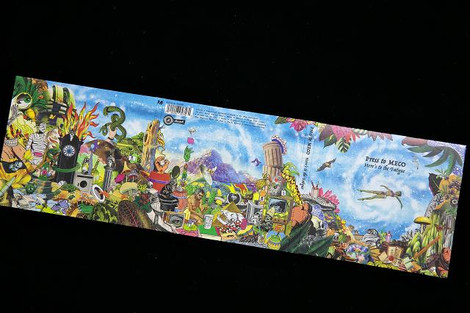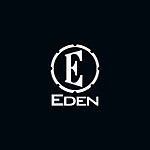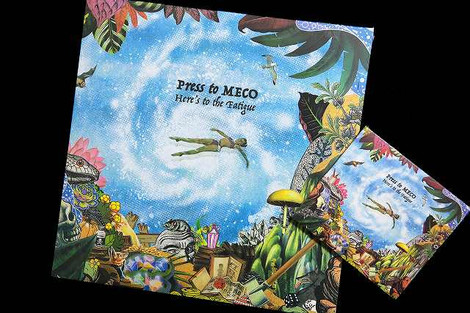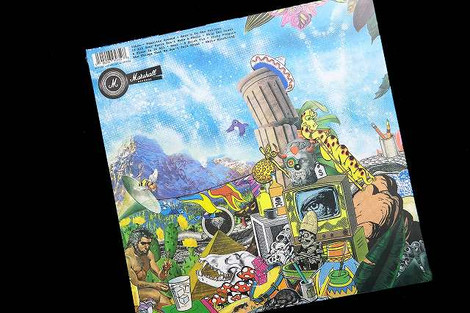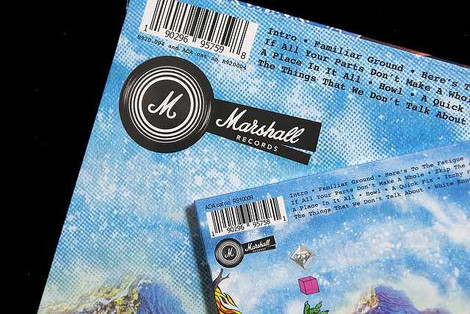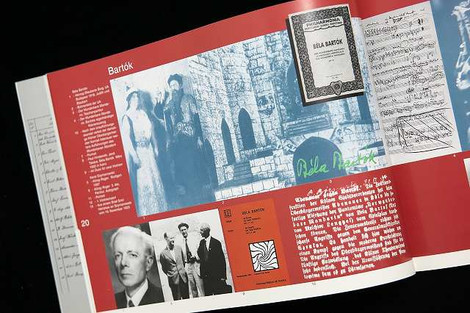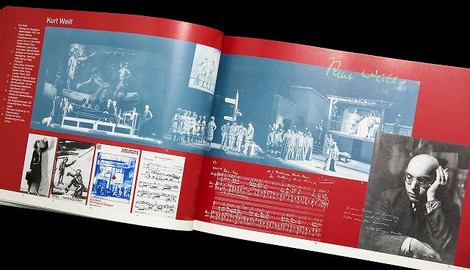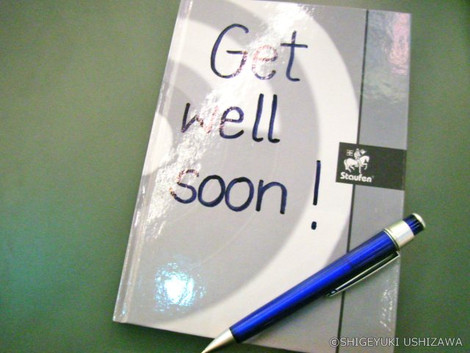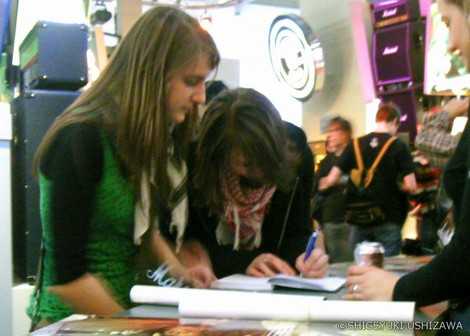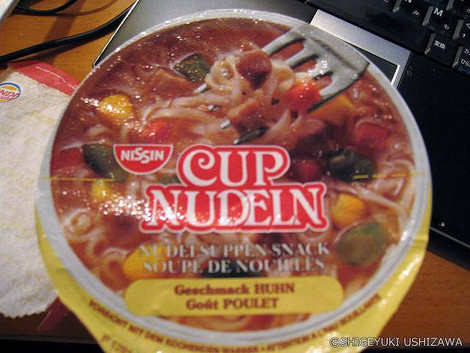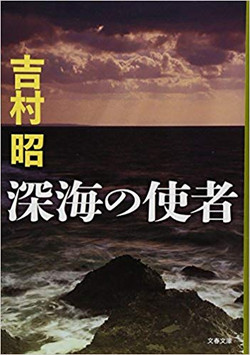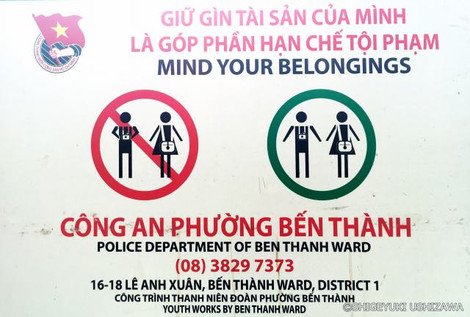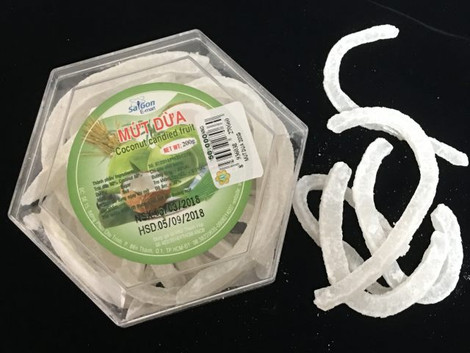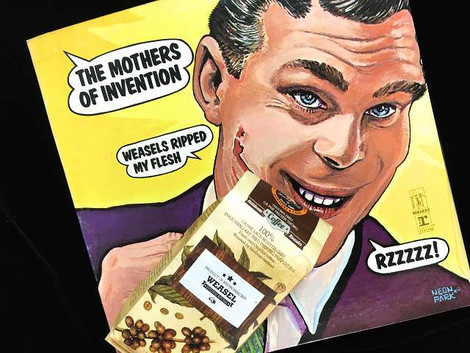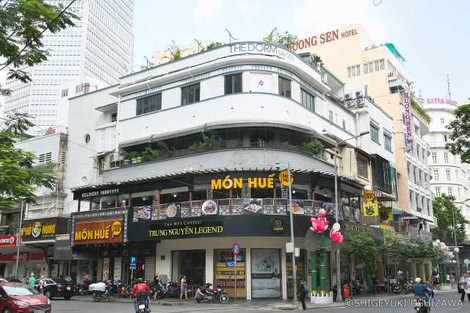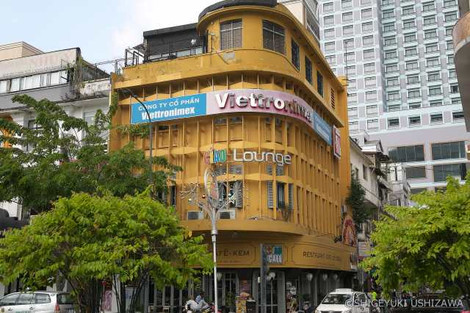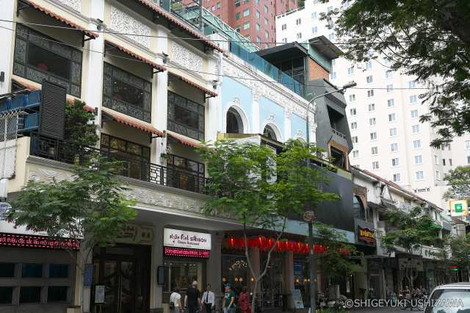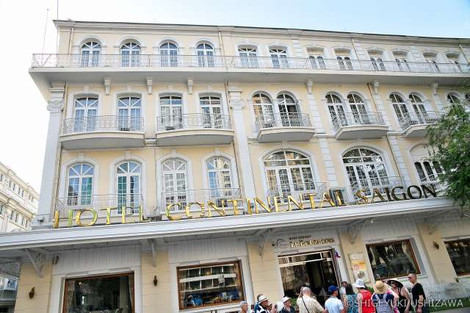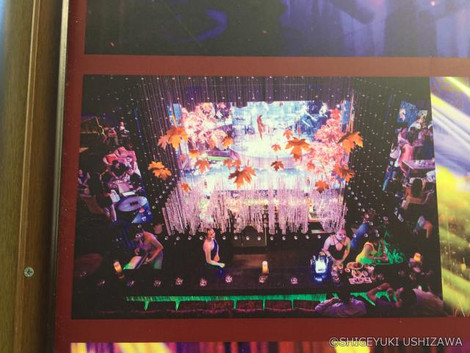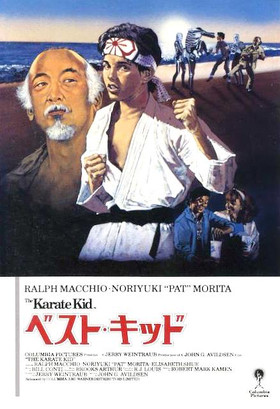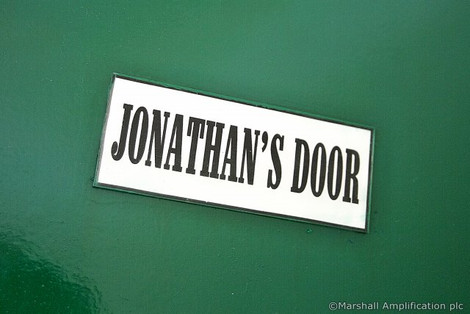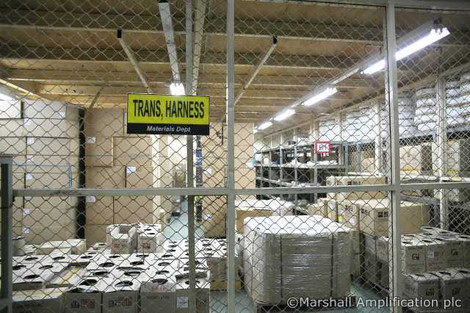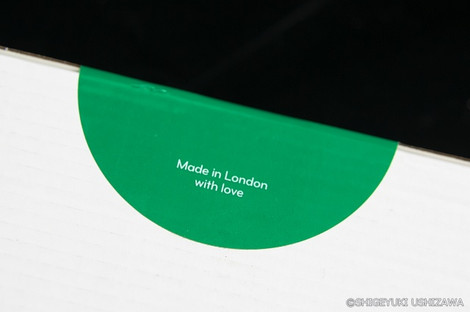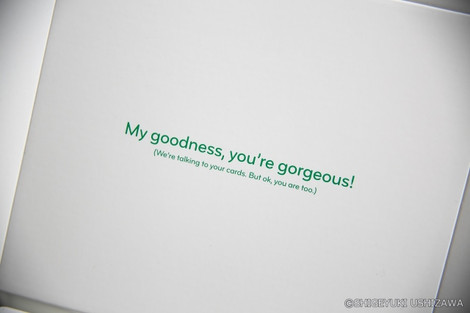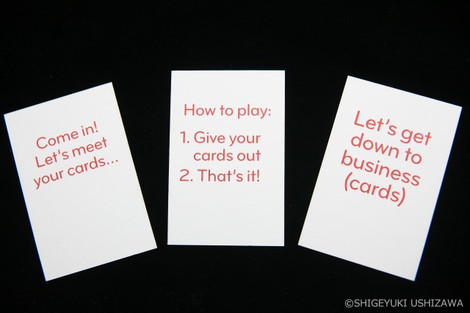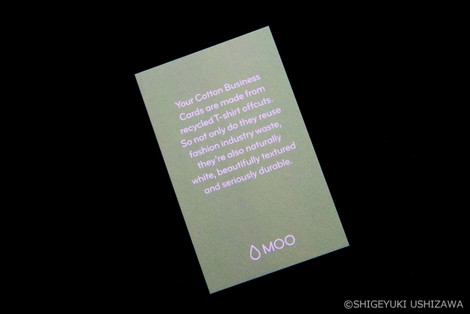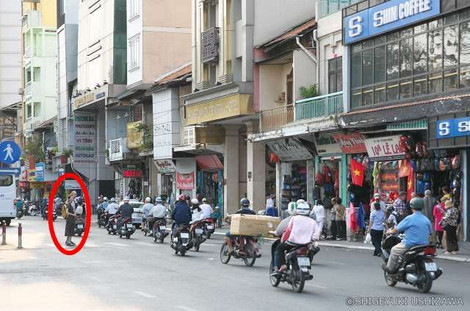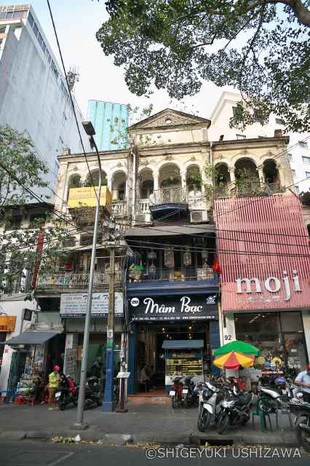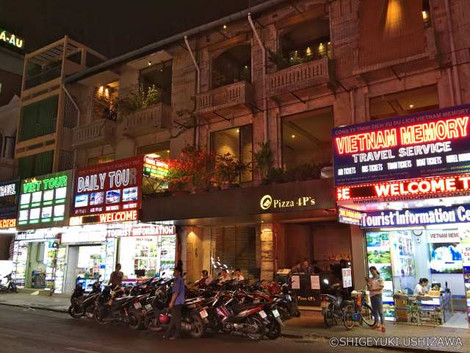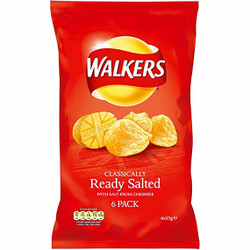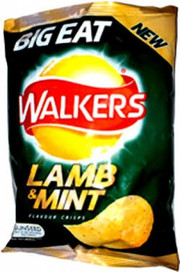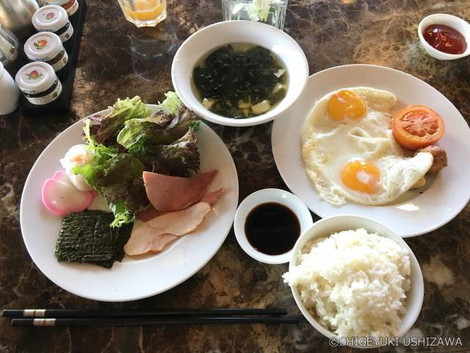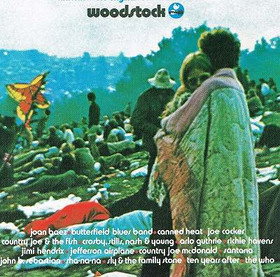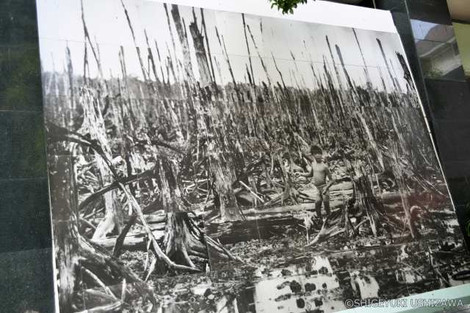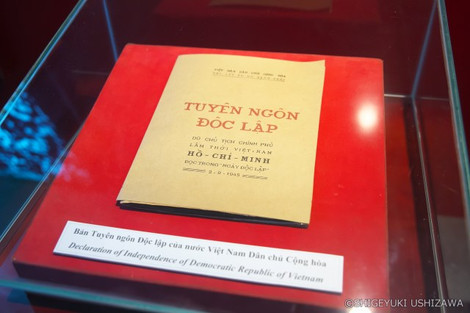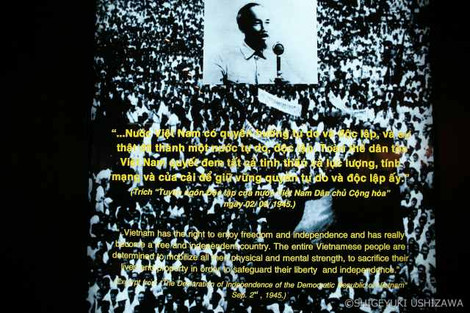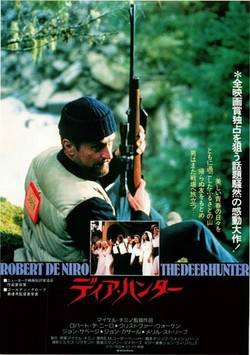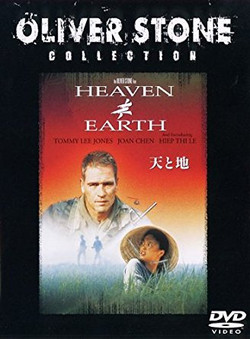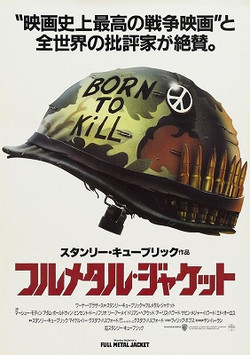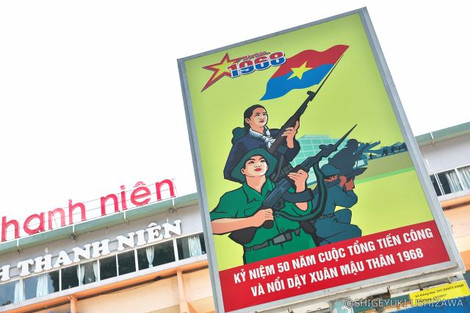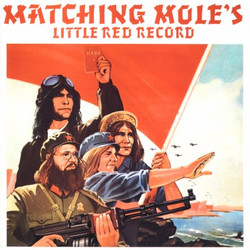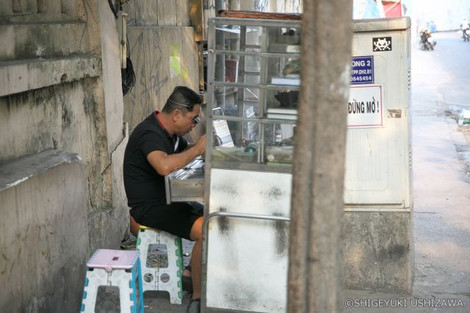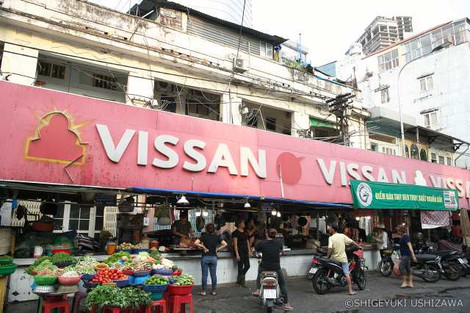VIDEO
あ、それと映画には出て来ないけど、サントラ盤に収録されているジョーン・バエズとジェフリー・シャートレフという人ガ歌う「Drug Store Truck Drivin' Man」という曲もスゴイよ。
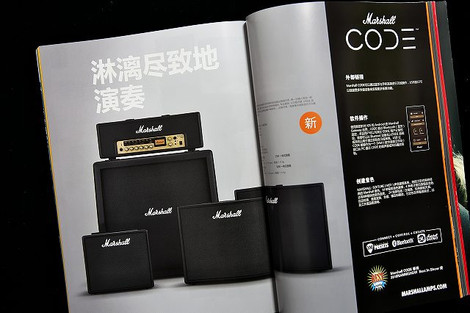 その扉のキャッチコピー「淋漓尽致演奏」。
その扉のキャッチコピー「淋漓尽致演奏」。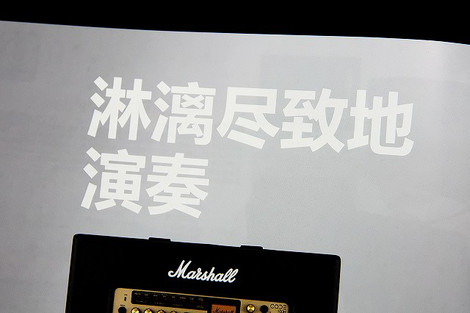 ココで謳っているCODEの特長は3つ。
ココで謳っているCODEの特長は3つ。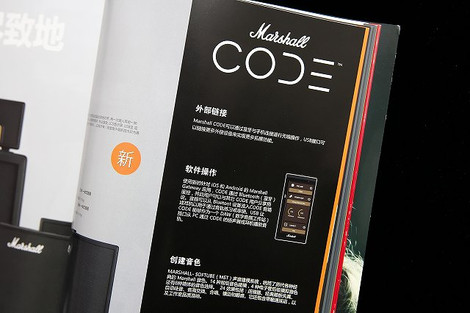 「吉他音箱」のコーナーにいってみよう!
「吉他音箱」のコーナーにいってみよう!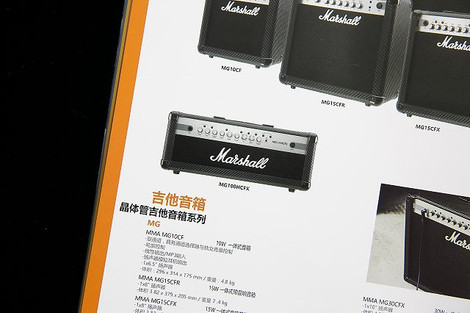 JVMのページ。
JVMのページ。 「吉他箱体」…もうコレは簡単。
「吉他箱体」…もうコレは簡単。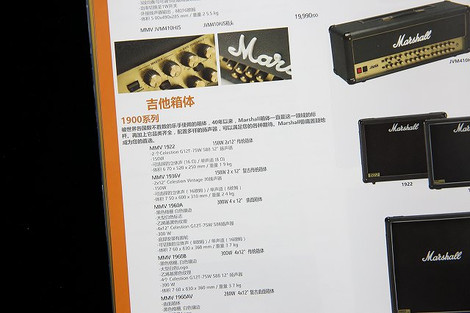 アコースティック楽器用のモデルのASのページ。
アコースティック楽器用のモデルのASのページ。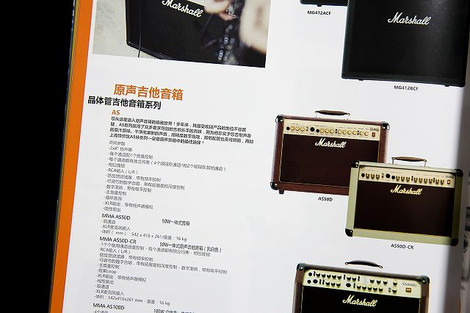 ミニ・アンプのMS-2のページ。
ミニ・アンプのMS-2のページ。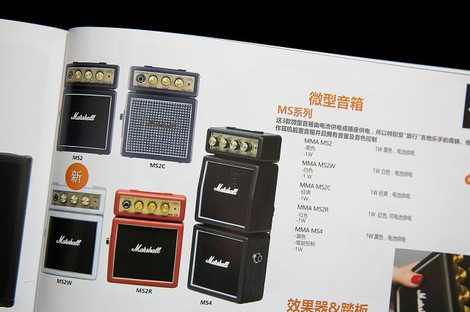 その下にあるのは「效果器&踏板」。
その下にあるのは「效果器&踏板」。
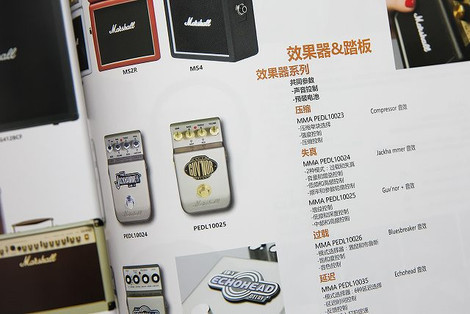 Lifestyle商品もチャンと載っている。
Lifestyle商品もチャンと載っている。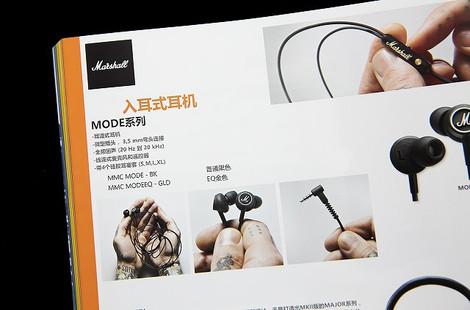 一方ヘッドホン。
一方ヘッドホン。 一方、Bluetoothスピーカーの方はいとも簡単。
一方、Bluetoothスピーカーの方はいとも簡単。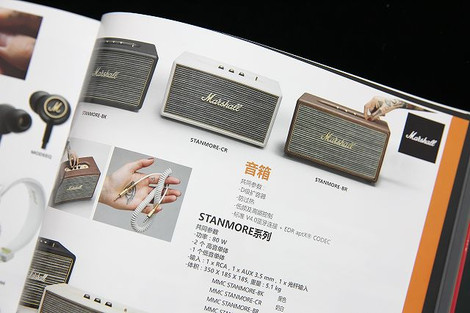 ドラムス関連はどうか。
ドラムス関連はどうか。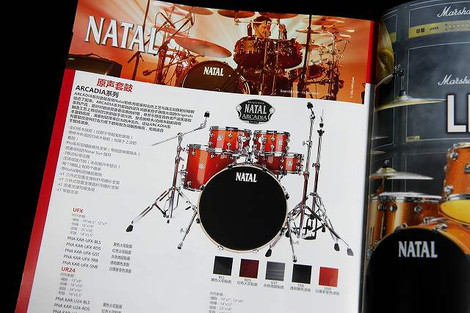 スネア・ドラムは「军鼓(チンクー…に聞こえる)」という。
スネア・ドラムは「军鼓(チンクー…に聞こえる)」という。 最後はEDEN。
最後はEDEN。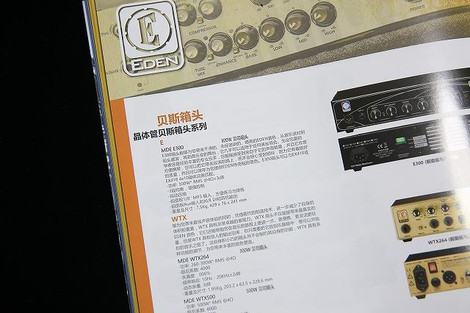 もうひとつ気になったのはコレ。
もうひとつ気になったのはコレ。 オモシロ半分で書き始めたこの記事…書き上げるのにかなり時間がかかっちゃった。
オモシロ半分で書き始めたこの記事…書き上げるのにかなり時間がかかっちゃった。