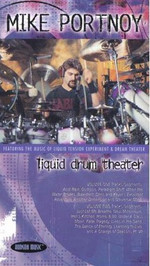【チャンネルMarshall Japan】思い出のMarshall
2002年に初めてMarshallの工場に行った時は感動したナァ。
ジムもまだ全然元気で、家にお呼ばれしてエラく緊張したっけ。
アレからもう数えきれないほど工場を訪れ、ドアの鍵の暗証番号を知るまでになってしまい、今では別段感動することがなくなってしまった。
それどころか、ジムと初めて仕事をさせて頂いてから21年…アータ、周りの人が物故したり、転職したりして行くウチに私もスッカリ古株になってしまったよ。
初めて行った時に驚いたのは、あのMarshallがほとんど手作りで生産されていたことだった。
今でも変わりはないが、基板周りを除いては工員さんがひとつひとつ丁寧にハンドメイドしていたのだ。
で、とりわけ目を惹いたのがカバリングのセクションで、木製のキャビネットにかぶせられたカバリング素材を切って、貼って、形を美しく整えていくサマはとても魅力的だった。
このカバリングのセクションが全ての工程の中で最も技術を要する…とその時聞いた。
今日はそんなカバリングのセクションを60年代に担当した人が語るMarshallの思い出。
Jim Nairnというお方。
このNairnという苗字の読み方がわからなくて困った。
ちょうど、GALA2でMarshallご一行と一緒だったので尋ねてみたのだが、「ネイルン」とも「ネイリン」とも…「ナーン」と読むのではないか?という説まで飛び出した。
取りあえずビデオの中では「ネイリン」さんとさせて頂いた。
ナーンかよくわからなかったんだけど、このお方、スゴイよね。
ハンウェルのジムの楽器店の頃からMarshallに勤めていたというんだから。
この赤い看板の床屋さんがそのジム・マーシャルの第1号店があったところ。
かつてはフィッシュ&チップス屋さんだったのだそうだ。
ココへ行った時も感動したわ~。
その時の様子はコチラ⇒【イギリス‐ロック名所めぐり vol.2】 マーシャルの生まれ故郷<後編>
 そして、コッチのジムは1965年、1959発表の瞬間に立ち会う。
そして、コッチのジムは1965年、1959発表の瞬間に立ち会う。
そのあたりのことを語っているのが『Marshall GALA2』の開演前、2番目に上映したビデオ。
いいね~。
初めて見た瞬間から字幕を入れて一人でも多くに人に見てもらいたいと思った。
この手のMarshallの歴史を記録するビデオなんてモノは作れるウチに作っておいて欲しい。
ところが!
おジイちゃん、すごいコックニー訛り!
しゃべっていることの意味はほぼ全部わかるのだが、字幕にするとなると正確を期さざるを得ない。
そこで、前回の記事に登場したフィリッパ姐さんにお願いしてトランスクライブ(文字起こし)してもらった。
それで何とか乗り切ることができた。
でもひとつ…うまく訳せなかった箇所があった。
それはジムが「And they announced the…who」というところ。
ココ、「(自分たちが)誰かを告げた」という意味と「The Who」というバンド名がシャレになっているワケ。
コレを何とか処理したかったんだけど時間切れ。
そんなこともありつつ字幕を完成させたのがこのビデオ。
お楽しみあれ!
YouTubeのチャンネルはコチラ⇒Marshal Japan